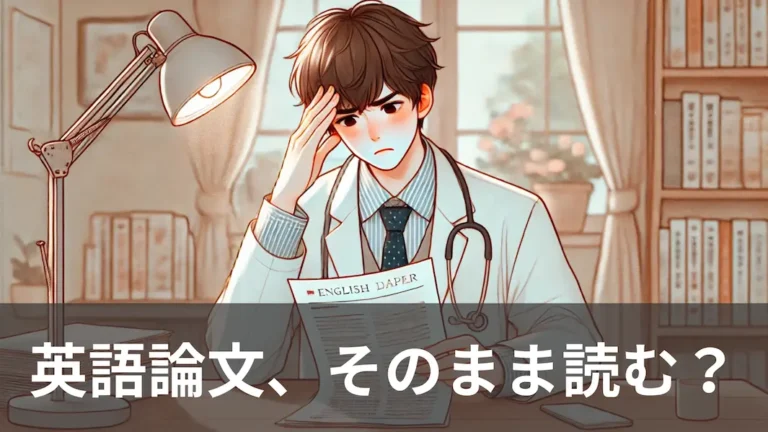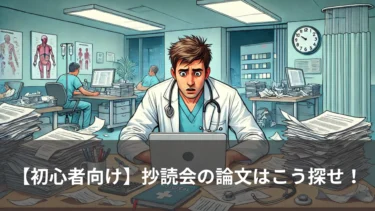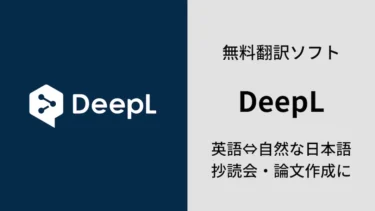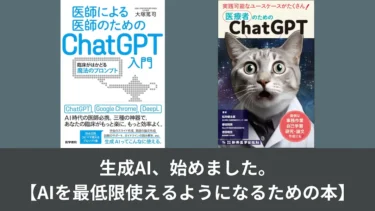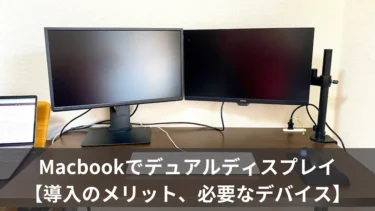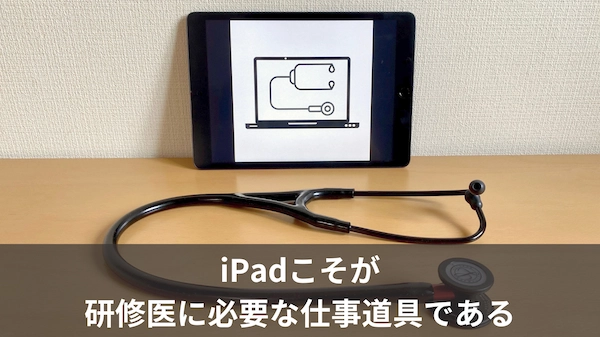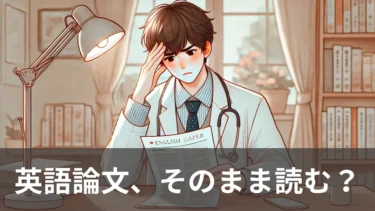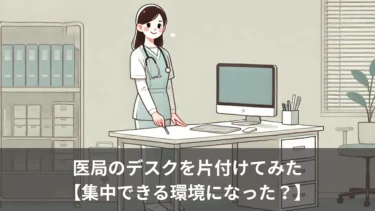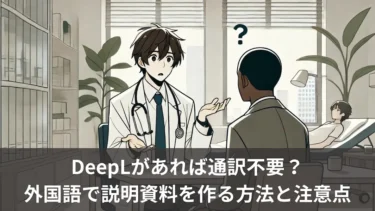「抄読会の論文を探さなきゃいけない…」
「上級医から『読んでみて!』と論文を渡された…」
他にもいろいろ業務があるのに…そんな中で英語論文を読み進めるのって、ハードルが高くないですか?
経験したことのある内容ならまだ読みやすいかもしれませんが、「ローテートが始まったばかりの科の論文」や「最新の知見についての論文」だったりすると、もうお手上げ。
せめて、「英文を読む」という苦労だけは取り除きたい。
せっかく翻訳ソフトもいろいろな種類があるんだから、使ってしまいたい。
でも、日本語に翻訳して読んでもいいのかな…?なんだかカッコ悪い気もするし。
今回は、こんな悩みを持った先生に向けた解説記事です。
結論から先にお伝えします。
- 「英語論文を日本語に翻訳して読む」ことのメリットとデメリット
- 生成AIで英語論文を要約するのはアリ?ナシ?
英語論文を日本語に翻訳して読むメリット

論文を読むハードルが下がる
英語論文をそのまま読むとなると、「①英語を解読する」「②そのうえで内容を理解する」というプロセスを踏むことになります。英語論文を読み慣れていれば気にならないのかもしれませんが、この2段階をこなしつづけるのってツラいんですよね。
それで論文を読むのを離脱してしまうぐらいなら、割り切って「①英語を解読する」は翻訳ソフト任せにしましょう。論文読みがサクサク進む経験をすると、次からも論文を読むのに抵抗がなくなります。
読みたい情報を拾いやすくなる
英語より日本語のほうが文字の種類が多いぶん、パッと見での可読性が高いです。「流し読みでも大事なところに目を止めやすい」のも、日本語で読むメリットではないでしょうか。
例えば、誤嚥性肺炎についての情報を、肺炎についてのレビュー論文から探すとしましょう。
何十ページもある中から「aspiration pneumonia」という文字列をイチイチ探すのって、うんざりしますよね。全文を日本語に変換して流し読みして、「誤嚥性肺炎」という文字を拾っていくほうが、よっぽど簡単に思えないでしょうか。
ただしこの点に関しては、英語・日本語を問わず、文字列検索機能を使うほうがスムーズかもしれません。
メモや抄読会に流用しやすくなる
翻訳文をどこかにコピペしておけば、あとから内容を見返しやすくなります。
ぼくが翻訳文をメモするのはこんなとき。
- 抄読会で使えるなと思ったら、全文翻訳してコピペをワードに保存しておく
- なんとなく面白かったなと思ったら、アブストラクトだけを翻訳して、内容の覚え書きを追記しておく
「どこかで読んだあの話、おもしろかったんだけど、英文をもう一回読み直して探すのがめんどくさいな…」
こうならないためにも、気になった部分はサクッと日本語に翻訳して保存しておくといいです。
多くの施設で行われている『抄読会』。研修医の頃は、抄読会の発表担当が特に嫌いでした。ローテート期間も短く、一般的な医学の勉強もしなきゃいけなくて忙しい。その上、よくわからないジャーナルから論文を探し出すなんて...苦痛でした[…]
英語論文を日本語に翻訳して読むデメリット

誤訳のリスクはある
誤訳のリスクは重々認識しておくべきです。
翻訳ソフトに丸投げしっぱなしで原文を一切確認しないのはオススメできません。
- 訳文を読んでいて違和感を感じたとき
- 自分で書いている論文に引用する部分
などは、原文を直接確認したほうがよいでしょう。
コピー&ペーストがめんどくさい
これも避けられないのですが、英文をいちいちコピペするのは手間です。論文のPDFデータの仕様によっては、余計な改行が入ってくることもあり、翻訳結果が微妙な感じになることも。
ただし、それでも無理して英文のまま読むよりはよっぽど時間短縮はできるはずです。
パソコンがないと論文を読めない
パソコン上で論文データから翻訳ソフトにせっせとコピペする作業して読み続けることになるわけで。
「紙の論文を持ち運んで読む」「iPadで読む」といったスタイルの人には向きません。
英語表現を自分の中に蓄積できない
「英文をそのまま読むからこそ、英語表現を自分に蓄積できる」というのはやっぱり否定できません。ぼく自身、上級医の先生から「論文を読んでいる中で使えそうな表現はどこかにメモしておくといい」と指導されたことがあります。
ただ、英語表現だけに限れば、英文校正サービスや生成AIの校正に任せてしまったほうが、結局はより洗練された(小慣れた)表現にしてくれます。むしろ、そうやって修正を受けた時の方が印象にも残りやすくて、身につくのでは?
オススメの翻訳ソフト『DeepL』
ぼくがオススメする翻訳ソフトは『DeepL』です。
英語論文を読むのって、はっきり言ってメンドくさいですよね。ぼくなんか、抄読会の準備は毎回てんやわんやでした。そもそも英文を読むのが大学受験以来だったし、医学英語なんて全然わからないし。そのうえ、いろんな科をローテートする[…]
無料でも使えますが、論文全体をひたすら翻訳し続けるなら有料版を契約したほうがスムーズです。
生成AIに論文を要約させるのって、どう?

このサイトでも、過去に「医師の生成AIの使い方の解説書籍」についての記事を書きました。
どうやら、医療現場に、静かに、そして確実に生成AIの波が押し寄せているようです。CareNetや日経メディカルなどで、生成AI系の記事を眼にすることが多くなったと感じています。ぼくも最近、生成AIを使おうと思い、勉強を始めました[…]
『ChatGPT』などの生成AIに、論文の内容を要約させることもできます。
書籍『医師による医師のためのChatGPT入門』でも、その方法が紹介されています。
ただ、ぼく自身は生成AIでの論文要約は行っていません。理由はふたつ。
第一に、生成AIの精度を完全には信じきれていないからです。AIが作った要約文を読んでも、「もっと大事な内容を取りこぼしていたりしないか」「内容が間違っていないか」といった点が気になってしまい、結局自分で原文をチェックすることになる気がするんですよね。
誤訳のリスクについても前述しましたが、やはりまだ現時点では生成AIにすべてお任せ、というのは考えものだと思います。
第二に、論文を読むときには、できるだけ全体に目を通したいという個人的なこだわりがあるからです。要約したときには省かれてしまいそうな、本筋とは外れた一文にハッと気付かされたり、患者の診療に活用できそうなアイデアにつながることをしばしば経験しています。
翻訳ソフトを使えば論文全体に目を通すのにたいして時間はかからなくなるので、最大効率を目指して要約した文だけ読むよりも、ほどほどのスピード感できっちり読み込んでいくほうが性にあっているんです。
「論文の内容をざっと掴みたいだけ」なら、生成AIに要約させればいいかもしれません。
しかし、「論文執筆のために、色々な論文を読み込んで使えそうなネタを探す」ときには、むしろ使わない方がいいと感じています。
まとめ
翻訳ソフトを使うかどうかは、目的に応じて考えるとよいでしょう。
- ある程度細かいところまで読みつつ、サクサク論文を読み進めたいなら翻訳ソフトを使う
- 英語力も高めたいなら英文のまま読むのがよさそう
- 論文の内容をざっくり把握したいだけなら、アブストラクトだけ翻訳するか、生成AIに要約させる
ちなみに、翻訳ソフトでサクサク論文を読み進めたいなら、デュアルディスプレイを導入した方が格段に効率がいいです。
デュアルディスプレイの導入については、こちらの記事をぜひご覧ください。
みなさん、1台はノートパソコンを持っているはず。けれど、デスクトップ型のパソコンを持っている人は、実はそう多くないのでは?「ノートパソコンで大体の仕事はなんとかなる」とは思います。しかし、ここであえて言いたい。デ[…]